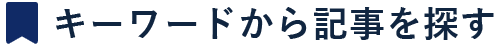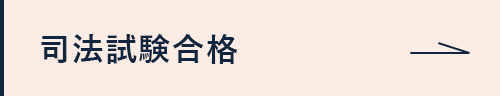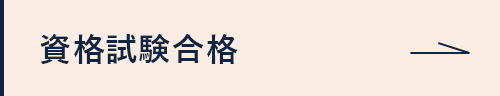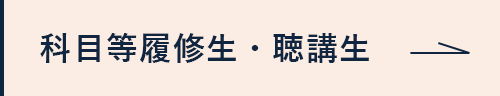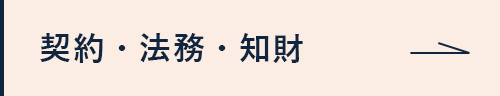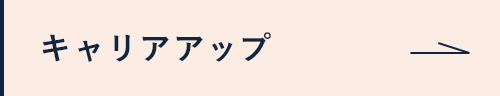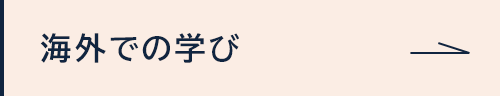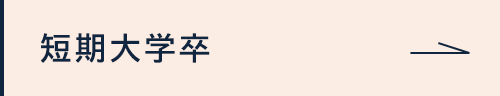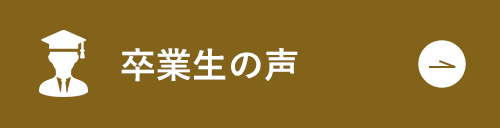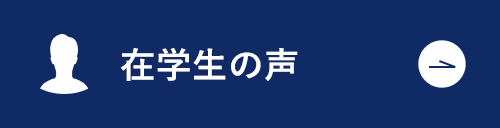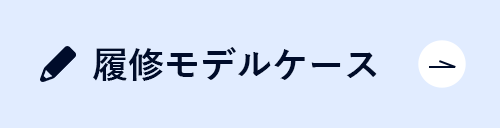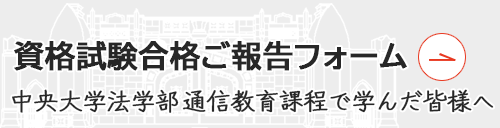卒業生の声 郷 博文 さん
「子どもたちの小さな声を拾える大人になりたい」
制度の網からこぼれ落ちそうな子どもたちに「もう一度やってみたい」と思える未来を届けたい——それが私の原動力となりました。
制度の網からこぼれ落ちそうな子どもたちに「もう一度やってみたい」と思える未来を届けたい——それが私の原動力となりました。
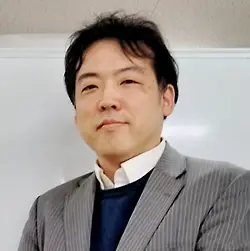
入学:2022年4月(3年次編入学)
卒業:2025年3月
就学時:30歳代
職業:塾経営
居住エリア:新潟県在住
(2025年5月掲載)
卒業:2025年3月
就学時:30歳代
職業:塾経営
居住エリア:新潟県在住
(2025年5月掲載)
中大通教で法律を学ぼうと思ったきっかけを教えてください。
私が中央大学法学部通信教育課程で法律を学ぼうと決めたのは、「子どもたちの小さな声を拾える大人になりたい」と強く感じたからです。私は新潟で個別指導塾イーラインONEを運営し、発達障害や不登校、家庭の事情で自信を失った生徒たちと日々向き合っています。彼らの中には、医療や福祉の公的支援の枠外にとどまり、制度にアクセスする以前に「自分には資格がない」と心を閉ざしてしまいがちです。大きな学力の遅れと自己否定感が結びつき、さらに社会から距離を置く——その悪循環を断ち切る鍵が、法律の知識と教育現場での実践をつなぐ視点だと気づきました。
中央大学は判例研究の厚みと通信教育の柔軟さを兼ね備えています。法律を体系的に学びながら、塾で子どもの声を聴き、学問で裏付けを得る。この往復運動は「机上の理論」を「現場の手立て」へ転換する機会と考えました。制度の網からこぼれ落ちそうな子どもたちに「もう一度やってみたい」と思える未来を届けたい——それが私の原動力となりました。
中央大学は判例研究の厚みと通信教育の柔軟さを兼ね備えています。法律を体系的に学びながら、塾で子どもの声を聴き、学問で裏付けを得る。この往復運動は「机上の理論」を「現場の手立て」へ転換する機会と考えました。制度の網からこぼれ落ちそうな子どもたちに「もう一度やってみたい」と思える未来を届けたい——それが私の原動力となりました。
レポート学習に取り組まれた感想を教えてください。
中大通教でのレポート学習は、慣れるまで少し時間がかかるかもしれません。専門用語の意味を調べたり、判例を丁寧に読み込んだり、引用方法を確認したりと、初めのころは一歩一歩進むような感覚で、「うまく書けるかな」と不安に感じることもありました。私自身も、はじめのレポートでは字数オーバーや論理のつながりに迷うことが多く、何度も先生からの赤ペンをいただきました。
それでも、焦らずに「まずは書いてみる」「先生のコメントを参考にして書き直す」を繰り返すうちに、少しずつ表現のコツが見えてきました。1年ほどで、レポートの骨組みが自然に頭に浮かぶようになりました。
通信教育過程では孤独になりがちです。是非、支部の勉強会は参加してください。様々な年齢の人たちが切磋琢磨しています。参加することで、同じ悩みを共有できました。ありがたいことです。
中央大学では、充実した判例教材と、忙しい方にも配慮された通信ならではの学びの仕組みが用意されています。序論・本論・結論の三段構成や、主張→根拠→具体例→まとめというシンプルな流れを意識するだけで、レポート作成がぐんとわかりやすくなります。提出後には指導教員からのあたたかいアドバイスが届き、ひとつひとつ改善を重ねられる安心感があります。
それでも、焦らずに「まずは書いてみる」「先生のコメントを参考にして書き直す」を繰り返すうちに、少しずつ表現のコツが見えてきました。1年ほどで、レポートの骨組みが自然に頭に浮かぶようになりました。
通信教育過程では孤独になりがちです。是非、支部の勉強会は参加してください。様々な年齢の人たちが切磋琢磨しています。参加することで、同じ悩みを共有できました。ありがたいことです。
中央大学では、充実した判例教材と、忙しい方にも配慮された通信ならではの学びの仕組みが用意されています。序論・本論・結論の三段構成や、主張→根拠→具体例→まとめというシンプルな流れを意識するだけで、レポート作成がぐんとわかりやすくなります。提出後には指導教員からのあたたかいアドバイスが届き、ひとつひとつ改善を重ねられる安心感があります。
レポートはどのくらいのペースで作成、提出していましたか?また、平均的な学習時間を教えてください。
大きな壁掛けカレンダーやスマホのスケジュール管理アプリを活用し、レポート提出の進捗を常に「見える化」していました。具体的には、1科目あたり2か月で2本のペースを基本とし、最終学年は年間で10~20本程度を提出。2科目を同時並行で学びながら、2~3週間ごとにどちらかの下書きを仕上げ、締切ぎりぎりにならないよう余裕を持って提出サイクルを回していました。
平日は1日あたり1~2時間を学習時間に設定。通勤や家事の合間にはスマホでレジュメを確認し、「ここまで終わったらカレンダーに✔」と小さな達成感を積み重ねました。教材の読み込み、判例チェック、アウトライン作成といった作業を細分化し、タスクごとに時間割を組むことで「今日は要件定義」「明日は引用スタイルチェック」という具合に迷わず取り組めました。
週末には土日それぞれ2~3時間を確保し、下書きのブラッシュアップや先生のコメント反映、引用文献の最終確認に集中。特に最終学年は提出本数が増えるため、「週のスケジュールにレポート作成ブロックを3枠入れる」など、カレンダー上で学習と生活のバランスを可視化しました。
大きなカレンダーとスマホアプリを併用して進捗管理を行うことで、「何をいつまでにやるか」が明確になり、仕事や家庭との両立も無理なく実現できました。レポート提出サイクルを習慣化することで、最終的には年間の提出本数が10本を超えても焦らずに対応できるようになり、学習効率と達成感が大きく向上しました。
平日は1日あたり1~2時間を学習時間に設定。通勤や家事の合間にはスマホでレジュメを確認し、「ここまで終わったらカレンダーに✔」と小さな達成感を積み重ねました。教材の読み込み、判例チェック、アウトライン作成といった作業を細分化し、タスクごとに時間割を組むことで「今日は要件定義」「明日は引用スタイルチェック」という具合に迷わず取り組めました。
週末には土日それぞれ2~3時間を確保し、下書きのブラッシュアップや先生のコメント反映、引用文献の最終確認に集中。特に最終学年は提出本数が増えるため、「週のスケジュールにレポート作成ブロックを3枠入れる」など、カレンダー上で学習と生活のバランスを可視化しました。
大きなカレンダーとスマホアプリを併用して進捗管理を行うことで、「何をいつまでにやるか」が明確になり、仕事や家庭との両立も無理なく実現できました。レポート提出サイクルを習慣化することで、最終的には年間の提出本数が10本を超えても焦らずに対応できるようになり、学習効率と達成感が大きく向上しました。
スクーリングの受講科目や科目試験の日程など、スケジュールはどのように決めていましたか?
スクーリングや科目試験の日程は、学習と日常生活のバランスを保つために、計画的に決めるようにしていました。決めておかないと、イレギュラー対応ができません。毎週1日は予備日を作り、計画通りにいかない場合は、予備日で対応しました。
毎年、年明けにシラバスが公開されると同時に、大きな壁掛けカレンダーにすべての候補日を書き出し、そして、それらの予定をスマホのスケジュールアプリにも入力し、どこでも確認できるようにしていました。
スケジュール管理の基準は、①前の年の仕事や家庭の予定と重ならない週末や連休を選び、そこに必修科目を優先的に入れます。空いている日には、自分の興味のある選択科目を入れるようにしました。また、②スクーリングが連続して疲れてしまわないように、できるだけ間に1日以上の休みを入れるように心がけました。
こうした工夫をすることで、学習のペースを崩さず、無理なく予定をこなすことができました。壁掛けカレンダーで全体を見渡しながら、スマホで細かい管理もできるので、安心して学びに集中することができました。
毎年、年明けにシラバスが公開されると同時に、大きな壁掛けカレンダーにすべての候補日を書き出し、そして、それらの予定をスマホのスケジュールアプリにも入力し、どこでも確認できるようにしていました。
スケジュール管理の基準は、①前の年の仕事や家庭の予定と重ならない週末や連休を選び、そこに必修科目を優先的に入れます。空いている日には、自分の興味のある選択科目を入れるようにしました。また、②スクーリングが連続して疲れてしまわないように、できるだけ間に1日以上の休みを入れるように心がけました。
こうした工夫をすることで、学習のペースを崩さず、無理なく予定をこなすことができました。壁掛けカレンダーで全体を見渡しながら、スマホで細かい管理もできるので、安心して学びに集中することができました。
受講したスクーリングの中で印象に残っている科目を教えてください。
私が最も印象に残っているスクーリング科目は、労働法(集団法)です。講義では、労働組合法や団体交渉権、争議行為の法的制限など、労働者が集団として権利を主張する仕組みを体系的に学びました。条文だけでは理解しきれない“現場感”を身につけられたのが大きな収穫でした。
特に印象的だったのは、米津先生の「生成AIの登場で、労働組合法や団体交渉権、争議行為の法的制限など、労働者が集団として権利を主張する仕組みが大きく変わる」というお話です。AIによるビッグデータ分析や自動交渉シミュレーションの活用が、従来の法解釈や交渉戦略にどのような影響を与えるのか──その可能性を考えるだけで怖くもあり、未来の法務像にワクワクしました。
また、実際の労働訴訟を題材に、論点整理から結論までをまとめる実践的なトレーニングがあり、「法的思考の組み立て方」を体得する機会にも恵まれました。
こうした学びを通じて、労働者の権利保護と使用者の経営自由とのバランスを法律的に調整する視点が育まれたと感じています。生成AI時代の労働法を見据えた知見は、今後の教育活動や法務実務にも可能性を感じました。
特に印象的だったのは、米津先生の「生成AIの登場で、労働組合法や団体交渉権、争議行為の法的制限など、労働者が集団として権利を主張する仕組みが大きく変わる」というお話です。AIによるビッグデータ分析や自動交渉シミュレーションの活用が、従来の法解釈や交渉戦略にどのような影響を与えるのか──その可能性を考えるだけで怖くもあり、未来の法務像にワクワクしました。
また、実際の労働訴訟を題材に、論点整理から結論までをまとめる実践的なトレーニングがあり、「法的思考の組み立て方」を体得する機会にも恵まれました。
こうした学びを通じて、労働者の権利保護と使用者の経営自由とのバランスを法律的に調整する視点が育まれたと感じています。生成AI時代の労働法を見据えた知見は、今後の教育活動や法務実務にも可能性を感じました。
お仕事がお忙しい中、学習を両立させる上で、心掛けた事などありましたら教えてください。

学習時の本棚
学習効率を高めるために、まず「優先順位の明確化」を行いました。月ごとに学習テーマを3つに絞り、重要度の低い内容は翌週以降に先送り。これによって、何を最優先すべきか常に意識でき、無駄なく学習を進められました。次に「音声録音&シャドーイング」を取り入れ、レポート執筆や判例整理の要点をスマホに録音。通勤や家事の合間に再生しながら、自分の声で口に出して復習することで、理解が飛躍的に深まりました。また、「ポモドーロ・テクニック」で時間管理を徹底しました。25分間集中してテキスト演習やアウトライン作成に取り組み、5分間の休憩を挟むサイクルを繰り返すことで、長時間でも疲れずに学習を継続できました。最後に「月次レビュー&リワード」を実施。月末に達成度を振り返り、達成できたテーマには小さなご褒美を設定することで、モチベーションを維持しやすくしました。これらの方法を組み合わせることで、忙しい日常の中でも効率的に学習を進め、確かな成果を実感できるようになりました。
中大通教で体系的に法律を学んだことで、ご自身に変化はありましたか?また、お仕事や日常生活にどのようなメリットがありましたか?
中央大学法学部通信教育課程で法律を体系的に学ぶことで、問題解決のアプローチが大きく変わりました。課題に直面した際に、「根拠となる法令は何か」「判例はどのような判断を示しているか」を意識して考えられるようになり、論点の抜けを防ぎつつ最適な解決策を導けるようになりました。
業務では、契約書や規約のリスク箇所を見逃さずにチェックできるようになり、取引先や顧客との交渉にも説得力が生まれました。報告書や提案書の作成においても、「序論・本論・結論」の構造を意識し、主張→根拠→具体例→まとめの流れで書くことで、読み手に伝わりやすい文章を作成できるようになりました。
日常生活では、契約やルールを確認する習慣が自然と身につき、トラブルを未然に防ぐ効果を実感しています。また、学習を継続する中で培った自己管理力は、仕事やプライベートでの目標達成にも役立ちます。目標設定→調査→分析→実行→振り返りのサイクルを意識することで、小さなタスクを着実にクリアし、達成感を得ながら成長を実感できるようになりました。
このように、法律学習で養った思考力や文書力、自己管理術は、業務効率の向上だけでなく、日常の選択や人間関係にも応用できる汎用性の高いスキルです。学んだ知識が生活のあらゆる場面で役立つことを実感しています。
業務では、契約書や規約のリスク箇所を見逃さずにチェックできるようになり、取引先や顧客との交渉にも説得力が生まれました。報告書や提案書の作成においても、「序論・本論・結論」の構造を意識し、主張→根拠→具体例→まとめの流れで書くことで、読み手に伝わりやすい文章を作成できるようになりました。
日常生活では、契約やルールを確認する習慣が自然と身につき、トラブルを未然に防ぐ効果を実感しています。また、学習を継続する中で培った自己管理力は、仕事やプライベートでの目標達成にも役立ちます。目標設定→調査→分析→実行→振り返りのサイクルを意識することで、小さなタスクを着実にクリアし、達成感を得ながら成長を実感できるようになりました。
このように、法律学習で養った思考力や文書力、自己管理術は、業務効率の向上だけでなく、日常の選択や人間関係にも応用できる汎用性の高いスキルです。学んだ知識が生活のあらゆる場面で役立つことを実感しています。
今後の夢や目標を教えてください。
私が運営する個別指導塾を拠点に、二つの学びを大切にしています。
まず一つ目は 法律の専門知識。発達障害や不登校のお子さんと向き合う中で、「こんなときはどんな制度が使えるだろう?」「保護者の方にはどう説明すれば安心していただけるだろう?」と思う場面が少なくありませんでした。中央大学で福祉法や労働法、知的財産法などを体系的に学ぶことで、塾の手続きや地域との連携をスムーズに進められる力を身につけたいと考えています。
二つ目は AIを使った学習サポートの開発に、創作活動を通じて、一人ひとりの学習履歴や気持ちの変化をデータでとらえ、最適な教材や励ましの言葉を自動で提案する仕組みを作りたいと思っています。その過程では、漫画やイラストを用いたオリジナル教材を自分で制作し、子どもたちの興味を引くコンテンツとして組み込む予定です。Pythonや機械学習の基本を学びながら、塾で小さなプロトタイプを動かし、講師のサポートと生徒の安心感を両立する方法を探っています。
この二つを組み合わせることで、「安心して学べる法的な土台」と「心に寄り添うテクノロジーと創作」の両方をそなえた、新しい教育の形を目指していきます。いつでも塾に立ち寄れる居場所を守りながら、少しずつ学びを深めていきたいです。
将来的に、子供のなかには米津玄師さんのような、才能の原石がいます。米津さんのような才能を100人作りたいです。
まず一つ目は 法律の専門知識。発達障害や不登校のお子さんと向き合う中で、「こんなときはどんな制度が使えるだろう?」「保護者の方にはどう説明すれば安心していただけるだろう?」と思う場面が少なくありませんでした。中央大学で福祉法や労働法、知的財産法などを体系的に学ぶことで、塾の手続きや地域との連携をスムーズに進められる力を身につけたいと考えています。
二つ目は AIを使った学習サポートの開発に、創作活動を通じて、一人ひとりの学習履歴や気持ちの変化をデータでとらえ、最適な教材や励ましの言葉を自動で提案する仕組みを作りたいと思っています。その過程では、漫画やイラストを用いたオリジナル教材を自分で制作し、子どもたちの興味を引くコンテンツとして組み込む予定です。Pythonや機械学習の基本を学びながら、塾で小さなプロトタイプを動かし、講師のサポートと生徒の安心感を両立する方法を探っています。
この二つを組み合わせることで、「安心して学べる法的な土台」と「心に寄り添うテクノロジーと創作」の両方をそなえた、新しい教育の形を目指していきます。いつでも塾に立ち寄れる居場所を守りながら、少しずつ学びを深めていきたいです。
将来的に、子供のなかには米津玄師さんのような、才能の原石がいます。米津さんのような才能を100人作りたいです。

プロンプト指導の際に作成したAIイラスト
生徒にプロンプト指導
状況説明から国語力アップをめざします。
暗い城壁のシルエットと対照的に、彼女自身が発する暖かいオーラと宝石の煌めきが際立ち、「闇の中で灯る希望」や「影を纏いながらも内に光を宿す人物像」を演出
入学を検討している方にメッセージをお願いします。

中央大学法学部通信教育課程は、先進的な教育スタイルを持つ学びの場です。現在、多くの通信制高校がその利便性を広めていますが、その先駆けとしての「通信教育」の歴史と実績が当課程にはあります。場所や時間にとらわれず学べるだけでなく、講義内容は常に最新の法改正や判例を反映し、深い理解へと導いてくれます。
卒業式で先生がお話しくださった「法学的な思考」の言葉が今でも心に残っています。直感だけでは解決が難しい問題でも、条文や判例という“道しるべ”をもとに筋道を立てて考えることで、論理的に解決策を導き出せる──その力が身についたことを、私自身、卒業後の日常や仕事の中で強く実感しています。
「漠然とした課題を整理できない」「答えが見えにくい問題に直面したとき、自信をもって考えを構築したい」──そんな思いをお持ちの方には、ぜひ中央大学法学部通信教育課程での学びをおすすめします。自分のペースで学びながら、確かな論理力と問題解決力を手に入れることができます。私は生徒から「生きた知識は、知恵となる」ことを学びました。知恵を生かせるような社会を作っていただきたいです。現代社会で求められる「筋道立てて考える力」を、あなた自身のものにしてください。
中央大学は、「才能の原石の【あなた】」を待ってます。
卒業式で先生がお話しくださった「法学的な思考」の言葉が今でも心に残っています。直感だけでは解決が難しい問題でも、条文や判例という“道しるべ”をもとに筋道を立てて考えることで、論理的に解決策を導き出せる──その力が身についたことを、私自身、卒業後の日常や仕事の中で強く実感しています。
「漠然とした課題を整理できない」「答えが見えにくい問題に直面したとき、自信をもって考えを構築したい」──そんな思いをお持ちの方には、ぜひ中央大学法学部通信教育課程での学びをおすすめします。自分のペースで学びながら、確かな論理力と問題解決力を手に入れることができます。私は生徒から「生きた知識は、知恵となる」ことを学びました。知恵を生かせるような社会を作っていただきたいです。現代社会で求められる「筋道立てて考える力」を、あなた自身のものにしてください。
中央大学は、「才能の原石の【あなた】」を待ってます。