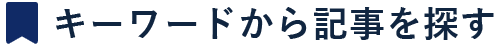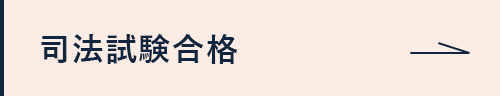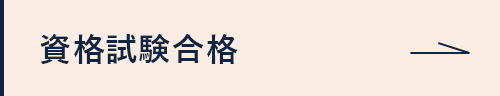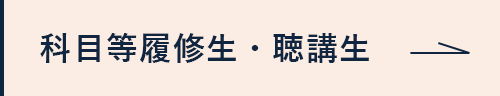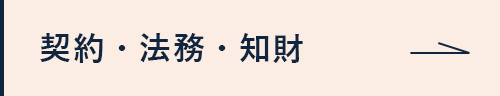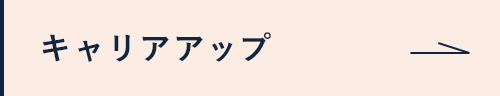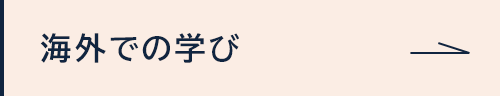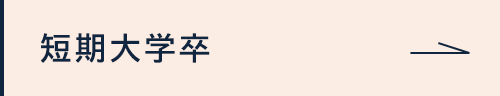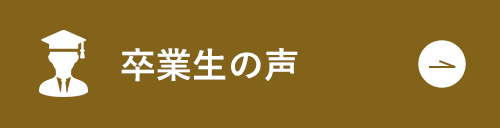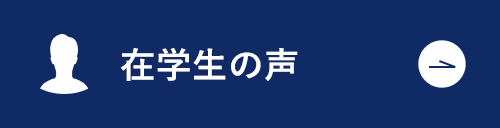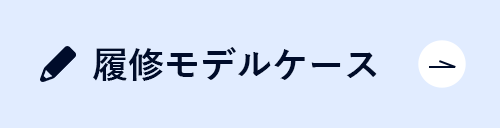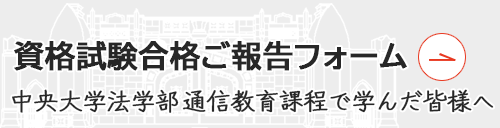卒業生の声 Takuya.E さん
入学した動機は生徒からの質問に自信を持って答えられるようにすることでした。今は質問に答える側として、どんな質問にも、一緒に考え、筋道立てて答えていくつもりです。

入学:2022年10月(3年次入学)
卒業:2025年3月
職業:愛知県立高等学校教諭(地歴公民科)
居住エリア:愛知県在住
(2025年4月掲載)
卒業:2025年3月
職業:愛知県立高等学校教諭(地歴公民科)
居住エリア:愛知県在住
(2025年4月掲載)
中大通教で法律を学ぼうと思ったきっかけを教えてください。
私は高等学校で教壇に立っていますが、生徒から質問を受けるたびに、自分には法的な知識がもっと必要であることを感じていました。そんな私が自信持って、明確に質問に答えられるような教員になるためには、法律を体系的に学ぶ必要があると強く思いました。そこで、仕事を続けながら法律を学べる機関を模索したところ、歴史と伝統があり、法的な専門知識や論理力、思考力を身につけることができる機関は「中央大学しかない!」と考え、入学を決意しました。私の選択は間違っていませんでした。ぜひ最後までお読みくだされば幸いです。
レポート学習に取り組まれた感想を教えてください。
法律の知識に乏しかった私は、専門科目【特に1群】のレポート学習で本当に苦労しました。初めのうちは、高校の授業でも教えている科目(『公共』・『政治経済』)でも扱う「環境法」から取り組みました。学校では公害については4大公害訴訟までしか扱わないのに、小賀野先生のテキストにはその後の三大交通公害訴訟や都市型複合大気汚染訴訟まで記載されており、学ぶやりがいを感じました。新島洋著の『青い空の記憶』も読み、公害問題に命がけで取り組んでいた様子もレポートに盛り込んだところ、高評価を得ることができ、出だしは悪くなかったのです。しかし1群科目となると、とたんに躓きました。中でも苦労したのが、学校の授業でも教えているはずの「憲法」でした。見出しのつくり方、文献からの引用の方法など基本的なことから、頂いた助言の通り取り組んだのですが、なかなか合格に至らず…。「白門」にある「道しるべ」に書いてあることも参考にしながら、まずは、自分自身が内容をしっかり理解をして、自分の言葉で表現することが大切であると考え、ようやく及第点に到達しました。それからは、レポートに合格できないことは格段に減りました。それでもまた【1群】の「民事訴訟法」のレポートが不合格となりました。そこで今度は、視点を変えて、違う科目の「民法3債権総論」の学習に取り組んだところ、だめな箇所がようやく分かってレポートを書き直したところ、「よく問題点に気づくことができましたね!このように添削者とのやり取りを通じて学習を進めながら“ご自身の気付きを得る”という醍醐味を堪能できたでしょうか」とおっしゃっていただいて合格できた時は本当に嬉しかったです。
レポートはどのくらいのペースで作成、提出していましたか?また、平均的な学習時間を教えてください。
不合格もいくつか経験しましたが、結局レポートは、全部で65通合格しています。レポートへの取り組みはルーティン化しており、今思うと生活の一部でした。月に8通書いた時もありましたが、平均すると1ヶ月に3通提出しています。平均的な学習時間は、日々の授業の準備もありましたので、それもあわせて平日は3~4時間程度。土日で部活動の指導がない時は5~6時間程度でした。
受講したスクーリングの中で印象に残っている科目を教えてください。

どのスクーリングも思い出深く、すばらしいものでした。その中でも夏休みに茗荷谷キャンパスまで受講しにいった時の、安井哲章先生が担当された「刑法各論」の夏期スクーリングが印象深いです。内容の難易度も高いものであったのですが、とても分かりやすく、基本から体系的に学ぶことができ、刑法が好きになりました。先生は休み時間も教室に来て板書をし、質問の時間も1人ひとりのために時間をさいてくださいました。安井先生は講義の中で「法律文章を書けるようになりたいと思ってスクーリングを受けに来たのでしょう」とおっしゃり、私たちを鼓舞してくれました。「もちろん書けるようになりたい!」と心の中で叫びました。講義が終わってもキャンパスの図書館にこもり、その後はファミレスで、閉店時間までずっと粘って勉強していました。試験の時は、先生が回答として何を求めているのかを考えながら、学んだことを思い出しつつ、頭をフル回転させて、時間いっぱいかけて答案を書きました。中央大学を選んで良かったと思えたスクーリングでした。このスクーリングでの体験を皮切りに、夏期スクーリング後も、仕事のスケジュールの合間を縫って、短期スクーリング、オンラインスクーリングに取り組みましたが、どの講義も私の視野を広げてくれる素晴らしい講義揃いでした。
また、最後に受講した、ゼミ形式による憲法の「演習」についても触れざるを得ません。担当された加藤隆之先生の講義は、筆舌に尽くせぬ「価値観が変わる」講義で、毎時間、目から鱗が落ちる、思い出に残る講義でした。加藤先生はもちろん、そこで出会って一緒に討論した同士たち、スクーリングを通して知り合った仲間は、私にとって一生の財産です。
また、最後に受講した、ゼミ形式による憲法の「演習」についても触れざるを得ません。担当された加藤隆之先生の講義は、筆舌に尽くせぬ「価値観が変わる」講義で、毎時間、目から鱗が落ちる、思い出に残る講義でした。加藤先生はもちろん、そこで出会って一緒に討論した同士たち、スクーリングを通して知り合った仲間は、私にとって一生の財産です。
スクーリングの受講科目や科目試験の日程など、スケジュールはどのように決めていましたか?
スクーリングの受講科目は、興味があって魅力を感じた内容の講義を選ぶようにしていました。科目試験の申込みは、レポートに合格をし、オンデマンドを受けるなどして受験資格を得たものはすべて受験するようにしていました。しかし、なかなか科目試験には受かりませんでした。今思うと、たくさん受験しようとせず、1回(土日あわせて)の科目試験ごとに、多くとも4つ程度にとどめて受験をしていればよかったと後悔しています。科目試験に合格するには一筋縄ではいかないからです。それだけやりがいがあり、受かった時の嬉しさはといえばそれはもうひとしおでした。
科目試験を受ける際、特に重要だと感じた学習方法はありましたか?
まずはクラウドキャンパスにアップしてある過去問に取り組んでから受験するようにしていました。同じ問題が出たらそれは幸運ですが、なかなかそうはいきません。しかも、すべての過去問を網羅して学習に取り組むことも至難の業です。それでも4つのレポートに合格をし、アップされてある過去問を一通りこなし、かつ、ある程度予測をたてて取り組めていた時はたいてい合格しました。過去問への取り組みが甘く、テキストも部分的にしか読めておらずに準備が間に合わなかった時は、受かったためしがありません。重要だと感じたことは、しっかりと試験の準備をした上で、試験当日は、勉強してきたことを思い出しながら、最後まであきらめず、出題した先生との対話と思って最後まで取り組むことです。自分ではだめだと思っても、その場でよく考えて、最後まで書き切ることで合格したこともあるため、最初から無理と思って白紙で出すなど言語道断です。書いているうちに頭が働いてきますし、たとえそれで不合格になったとしても、同じ問題が出たら、次は合格できるようにしっかりと復習し、次回の試験につながると考えることが重要です。そうしながら、繰り返し受験をすることで、科目試験の合格を積み重ねてきました。試験のチャンスは複数回あるので、今回はだめでも次は受かる!という精神で受け続けることが大切です。
お仕事がお忙しい中、学習を両立させる上で、心掛けた事などありましたら教えてください。
仕事が高校の先生であるため、担当の部活動の大会と、スクーリングや科目試験の日程が重なった場合は、仕事を優先せざるを得なかったため、スクーリングや科目試験が仕事と重ならないように、早めに予定を立てるようにしていました。中央大学での学習日程は早めに示されるため安心です。日頃の勉強時間の確保の方法は、早朝に喫茶店やファミレスで勉強し、仕事の帰りに図書館に寄るなどして時間を有効に使うように心がけていました。土日に日程があえば、学生会支部主催の学習会にオンラインで参加していました。支払は3000円/年最初に払えば何度でも受講できるため、申し込むことをおすすめします。この学習会にもとても感謝しています。仕事柄、ちょうど自分が高校で教える単元が、取り組んでいる科目と重なる時は一石二鳥という幸運もありました。
中大通教で体系的に法律を学んだことで、ご自身に変化はありましたか?また、お仕事や日常生活にどのようなメリットがありましたか?
価値観が大きく変わった気がします。これまで自分が正しいと思っていたことも、学習が進めば進むほど自分の価値観はいかに薄っぺらなものであるかに気がつきました。中央大学での勉強の日々はそのことに気がつく連続であったため、その都度調べては深く考え、の繰り返しでした。1つ例を挙げますと、朝日訴訟といえばプログラム規定説を採った、と解釈していました。それが違うことをオンデマンド講義で知り、質問用紙を使って「朝日訴訟」について質問してみました。回答は次の通りでした。「より深く法学部で専門的に憲法を学ぶ立場からは、朝日訴訟は完全なプログラム規定説を採っているとはいえない」と。つまり最高裁判決は裁判規範性を肯定しているわけです。これからは自分が質問に答える立場です。今後は今の自分の理解はこれでいいのかを自問自答しながら、何が正しいのかを筋道立てて考えていくつもりです。入学した動機は生徒の質問に答えられるようすることでした。今は質問に答える側として、どんな質問にも、一緒に考え、筋道立てて答えていくつもりです。それでも、知らないことは知らないと謙虚に答え、勉強を続けていくつもりです。中央大学の先生方は、決して妥協をゆるさず、厳しくも暖かい指導をしてくださる先生ばかりでした。私も中央大学で学んだ経験から、日々接する生徒たちを良い方向に導く働きかけをしていきたいです。中央大学での学習を最後までやり切ったことで、今後の仕事や日常生活において、困難に出くわした時には、自分の価値観のみにとらわれず、既存の価値観を疑いながら筋道立てて考えて、解決策を模索していくことができそうに思います。
今後の夢や目標を教えてください。
法的な思考を身につけることができた気はしますが、知識がまだまだ不足しています。卒業したことがゴールではないため、働きながら大学院に行ったり、司法試験に挑戦したり、私の学ぶ意欲はつきません。当面の目標は、日々接する生徒たちを、良い方向に導く授業・指導をしていくことです。そのために私は学び続けます。何年か経ち、定年退職をしてゆとりができた時には、非常勤講師の立場として教壇に立ちながらも、法曹関係の仕事に多少でも携わることが夢です。
入学を検討している方にメッセージをお願いします。

科目試験の難しさは半端ではありません。それでも試験に合格し、卒業することは不可能ではありません。私はそう考えて、卒業できることを信じて、志望動機をしっかり練って提出をし、入学を決意しました。入学を検討し、がんばってみようかな、と思っている方は即行動です。初めのうちは自分がとりかかりやすいと感じる科目のレポートやスクーリングから始めると良いです。まずレポートが1通受かればもう大丈夫です。そしてどれかスクーリングに参加したらもう軌道に乗ります。スクーリングで知り合った仲間同士たちもいて、一緒に励まし合ってがんばれました。仕事をしながらがんばっているのは自分だけではないと思えましたし、中央大学では、自分のペースで仕事をおろそかにせずに勉強に取り組むことができます。レポートは好きな時間に書けますし、計画的にスクーリングに参加するなどすれば、十分勉強時間を確保できます。ぜひ中央大学での学びをやり切った達成感を味わいませんか。