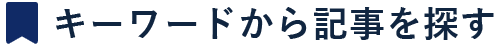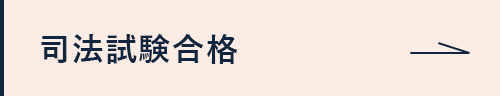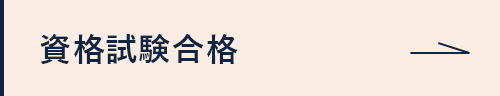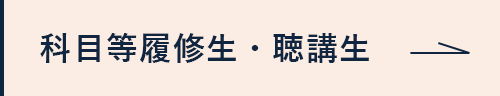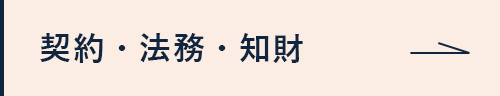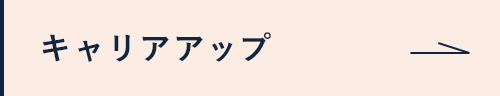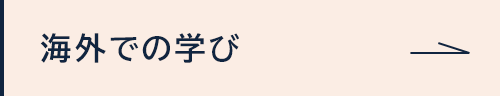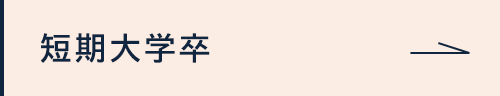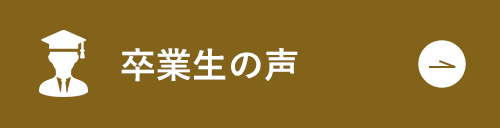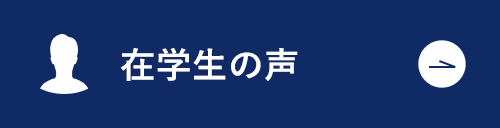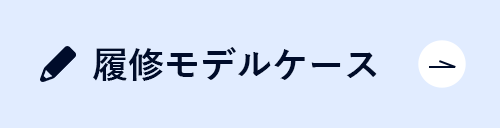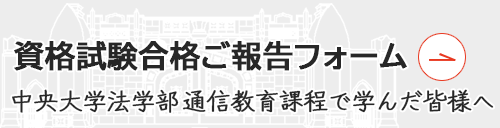卒業生の声 岡田 祐子 さん
今まで知らなかった世界を知ること、新たな考え方に触れることは、いくつになっても楽しいものです。法律だけでなく、今後も学び続けることができる大人でありたいです。

入学:2022年4月(3年次編入学)
卒業:2024年3月
就学時:30歳代
職業:国家公務員
居住エリア:東京都在住
2023年度成績優秀者として卒業
(2024年5月掲載)
卒業:2024年3月
就学時:30歳代
職業:国家公務員
居住エリア:東京都在住
2023年度成績優秀者として卒業
(2024年5月掲載)
中大通教で法律を学ぼうと思ったきっかけを教えてください。
公務員という仕事柄、元々法律は身近なものだったのですが、公務員試験の勉強が独学だったこともあり、いずれは法律を体系的に学んでみたいなと漠然と考えていました。そのような思いを抱えたまま30代を迎え、何か新しいことに挑戦したい、社会人としてプラスアルファの力を付けたい、と思っていた折に「人生を変える8万円」という広告を目にし、そのキャッチフレーズに惹かれて入学を検討しました。
他大学とも比較して、学費が安いだけでなく、オンデマンドやオンラインなどのスクーリングが充実しており、平日に通学しなくても卒業が可能であったことから、中央大学への入学を決めました。
他大学とも比較して、学費が安いだけでなく、オンデマンドやオンラインなどのスクーリングが充実しており、平日に通学しなくても卒業が可能であったことから、中央大学への入学を決めました。
レポート学習に取り組まれた感想を教えてください。
先輩方のRESTUDYを読んで覚悟はしていたものの、評価の厳しさに驚きました。私は3月末に入学願書を送ったのですが、最初に取り組んだ「法学入門」のレポートで不合格が続き、5月試験どころか7月試験すら受けられず、途方に暮れたのを覚えています。
しかし同時に、丁寧に添削してくださるインストラクターの先生方の熱意に感激しました。私のレポートと同じくらいの長文で講評を下さる先生もいらっしゃり、先生方のご指導のもと改めて教科書を読み直したり、表現を工夫したりすることで、レポートが改善していくのを実感できました。厳しいお言葉もたくさんいただきましたが、レポート学習は、インストラクターの先生方とコミュニケーションをとりながら学習できる素晴らしい機会でした。
しかし同時に、丁寧に添削してくださるインストラクターの先生方の熱意に感激しました。私のレポートと同じくらいの長文で講評を下さる先生もいらっしゃり、先生方のご指導のもと改めて教科書を読み直したり、表現を工夫したりすることで、レポートが改善していくのを実感できました。厳しいお言葉もたくさんいただきましたが、レポート学習は、インストラクターの先生方とコミュニケーションをとりながら学習できる素晴らしい機会でした。
レポートはどのくらいのペースで作成、提出していましたか?また、平均的な学習時間を教えてください。
レポートは1か月に2~3本の提出を目標にしていました。しかし、当初は構成や下調べに時間をかけ過ぎてしまい、思うように書き進められなかったため、途中からは簡単に構成を組んだらまず書き始めることにしました。書けるだけ書いて、後で追加の文献を読んだり、不要な部分を削ったりして文字数を整理することで、少しずつ提出のペースを掴めていったように思います。レポート作成時は、リーガル・リサーチを活用し法学雑誌(ジュリストや法学教室など)も参照しました。判例や論点ごとの解説、最新の法改正情報などが掲載されており、とても勉強になりました。
学習時間は、元々朝型だったため、平日は朝1時間半、通勤で往復1時間、夜は30分程度を確保し、主に教科書や参考書の精読、オンデマンドスクーリングの受講、レポートの下調べに充てていました。加えて朝の勉強後は、朝食やお弁当を作りながら、オンデマンドやメディア教材で理解しにくかった部分を繰り返し聴くなど、隙間時間を活用しました。
休日は5~6時間程度を確保して、主にレポートの作成をしていました。
学習時間は、元々朝型だったため、平日は朝1時間半、通勤で往復1時間、夜は30分程度を確保し、主に教科書や参考書の精読、オンデマンドスクーリングの受講、レポートの下調べに充てていました。加えて朝の勉強後は、朝食やお弁当を作りながら、オンデマンドやメディア教材で理解しにくかった部分を繰り返し聴くなど、隙間時間を活用しました。
休日は5~6時間程度を確保して、主にレポートの作成をしていました。
スクーリングの受講科目や科目試験の日程など、スケジュールはどのように決めていましたか?
スクーリングは、まず受講したい科目を全て洗い出し、年度初めに計画を立てました。優先順位は、第1に休日開講の対面・オンラインスクーリング、第2にオンデマンドスクーリング、として受講科目を選んでいたのですが、その際に重視していたのは、科目試験日程との兼ね合いです。試験対策の大変さを考えると1回(2日間)で4科目の受験が限度と考えていたので、科目試験とは別日程で試験を実施する対面・オンラインスクーリングを活用しながら、一気に何科目も受験しなくていいように工夫していました。
また、科目試験は年4回ありますが、5月と7月、11月と1月の試験間隔は2か月程度しかありません。そのため、時期によってオンデマンドスクーリングを受講する数を調整しました。具体的には、第1期(7月試験)と第3期(1月試験)は最大2科目、第2期(11月試験)と第4期(5月試験)は最大3科目を目安に受講していました。1期3科目の受講は若干きついですが、第2期、第4期であれば試験の準備期間は十分に取れるので、私の場合はこのペースが丁度良かったように思います。
その他、レポートのみで試験に臨む科目については、レポートが合格でき次第、直近の試験を受けていました。スクーリングも試験も、申込日程は自分で把握しておかなければならないので、こまめに「手続カレンダー」を確認することを心掛けました。
また、科目試験は年4回ありますが、5月と7月、11月と1月の試験間隔は2か月程度しかありません。そのため、時期によってオンデマンドスクーリングを受講する数を調整しました。具体的には、第1期(7月試験)と第3期(1月試験)は最大2科目、第2期(11月試験)と第4期(5月試験)は最大3科目を目安に受講していました。1期3科目の受講は若干きついですが、第2期、第4期であれば試験の準備期間は十分に取れるので、私の場合はこのペースが丁度良かったように思います。
その他、レポートのみで試験に臨む科目については、レポートが合格でき次第、直近の試験を受けていました。スクーリングも試験も、申込日程は自分で把握しておかなければならないので、こまめに「手続カレンダー」を確認することを心掛けました。
受講したスクーリングの中で印象に残っている科目を教えてください。
全ての講義が印象に残っているのですが、刑法総論の只木先生のオンデマンドスクーリングでは、刑法の奥深さを味わうことができただけでなく、通説とされているものの不確実性を知り、いかに自分の頭で考えることが大切かを思い知らされました。また、外国法研究の佐藤先生や国際法の雨野先生は、オンラインスクーリングで昨今の国際情勢も踏まえた深い講義をしていただき、質問にも丁寧に対応していただいたことが印象に残っています。警察行政実務の高木先生は、あまり馴染みのない警察行政についてわかりやすく解説していただいたほか、朝の通学時間に偶然ご一緒する機会があり、講義に関することや仕事のことなどをお話しできたのが思い出です。
ちなみに、対面やオンラインのスクーリングでは、積極的に講義に参加するため、毎日1回は質問をするように心掛けていました。また、対面スクーリングの際は基本的に1番前の席に座り、先生からマンツーマンで講義を受ける気持ちで受講していました。1番前の席は先生と物理的に距離が近いため質問をしやすいだけでなく、先生から声をかけていただけることも多々あり、モチベーションを保つことにも繋がりました。
ちなみに、対面やオンラインのスクーリングでは、積極的に講義に参加するため、毎日1回は質問をするように心掛けていました。また、対面スクーリングの際は基本的に1番前の席に座り、先生からマンツーマンで講義を受ける気持ちで受講していました。1番前の席は先生と物理的に距離が近いため質問をしやすいだけでなく、先生から声をかけていただけることも多々あり、モチベーションを保つことにも繋がりました。
第一線でお仕事をしつつ最短の2年でご卒業されました。最短卒業を目指して心掛けた事などありましたら教えてください。
初めから最短卒業を目指していたわけではなかったのですが、勉強を進めるにあたって心掛けたことといえば、毎日勉強する習慣を崩さなかったことと、睡眠時間を削らなかったことです。毎日の勉強については、どんなに仕事が忙しくても、短時間でも勉強時間を確保することで、「少しずつでも毎日前進している」という自信に繋がりました。睡眠時間については、寝不足のまま勉強を続けてもどこかで息切れしてしまいますし、何より体調を崩してしまったら本末転倒なので、仕事で帰宅が遅くなった場合には翌朝の勉強時間を短縮して寝ることを優先し、その分休日に勉強時間を追加していました(試験前は平日も多少無理をせざるを得ないこともありましたが...)。
また、通教の指定教科書の中には、難解なものや、とてつもなく分厚いものもありました。その場合は途中で挫折しないための工夫として、市販の薄い入門書を読んでから教科書を読むようにしていました。一見時間がかかりそうですが、薄い本であれば短時間で読めますし、全体像を頭に入れてから教科書を読むことで、理解が深まったように思います。
試験対策においては、過去問が非常に役に立ちました。答え合わせはできないものの、自分で六法を引きながら実際に解答を作成してみることで、どのような理解が不足しているのかに気づくことができます。論証など、ある程度自分の中で解答を用意しておくべき(暗記しておくべき)部分については、自分なりの論証を作成後、読み上げてスマートフォンに録音して何度も聞きなおし、暗唱することで理解を定着させていました。書くより時間がかからないので、おすすめです。
また、通教の指定教科書の中には、難解なものや、とてつもなく分厚いものもありました。その場合は途中で挫折しないための工夫として、市販の薄い入門書を読んでから教科書を読むようにしていました。一見時間がかかりそうですが、薄い本であれば短時間で読めますし、全体像を頭に入れてから教科書を読むことで、理解が深まったように思います。
試験対策においては、過去問が非常に役に立ちました。答え合わせはできないものの、自分で六法を引きながら実際に解答を作成してみることで、どのような理解が不足しているのかに気づくことができます。論証など、ある程度自分の中で解答を用意しておくべき(暗記しておくべき)部分については、自分なりの論証を作成後、読み上げてスマートフォンに録音して何度も聞きなおし、暗唱することで理解を定着させていました。書くより時間がかからないので、おすすめです。
中大通教で体系的に法律を学んだことで、ご自身に変化はありましたか?また、お仕事や日常生活にどのようなメリットがありましたか?
仕事においては、今まで以上に法律の根拠を意識しながら業務にあたるようになりました。また、講義やレポート学習を通じて、1つの事柄でも様々な学説があり、判例があり、その判例が覆されることもあり、それらの判例に対して相反する評価があることを学べたことで、他者の多様な考え方に対して向き合う姿勢が身に付いたように思います。日常生活においては、日々の出来事やニュースに対して個人的な感想を抱くだけでなく、どんな法律・条文が関係しているのか、どんな論点があり、自分はどう考えるのかを自然と意識するようになりました。自宅にいるときは今でも大学の教科書や六法を持ち出し、夫と議論することもあります。
今後の夢や目標を教えてください。
現在は法律から離れた勉強をしているのですが、仕事柄法律が身近な環境にいるので、中大通教で学んだ知識をアップグレードしながら、いずれは法律関係の資格に挑戦したいと思っています。また、法律だけでなく、今後も学び続けることができる大人でありたいです。
入学を検討している方にメッセージをお願いします。
私は約10年前に他大学を卒業しましたが、中大通教は、通学課程と同じくらいしっかりと勉強する必要があると実感しました。また、レポートに取り組まなくても誰からも注意されないのですから、常に自分との闘いとなり、通学課程よりも厳しいものがあるかもしれません。しかし、熱意ある先生方の講義はとても刺激的で、そのおかげで法律という学問を好きになることができましたし、インストラクターの先生方の厳しくも丁寧なご指導は、社会人としての慣れが生じていた私を叱咤激励してくれる、大変有難いものでした。そして何より、今まで知らなかった世界を知ること、新たな考え方に触れることは、いくつになっても楽しいものです。入学を迷われている方は、ぜひ一歩踏み出してみてください。きっと自分の世界が広がります。